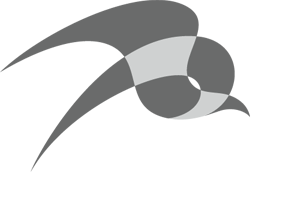全ての病気の克服に向けて
新たな科学分野「ヒューマン・メタバース疾患学」の創成
私たちは、発生・生殖・老化という生命の時間軸に着目し、一人ひとりの体内で生じる病気の発症のプロセスを包括的かつ連続的に理解する新たな科学分野「ヒューマン・メタバース疾患学」を創成します。このメタバースを用いた医学研究によって、個別化予防法や根治的な治療法の開発に取り組み、すべての病気の克服を目指します。
まず研究対象とするのは、肝疾患、肥満、認知症、網膜・視神経変性、心不全、変形性関節症など、多くの人が加齢とともに悩まされる病気です。
この拠点には多様な分野の研究者が集い、「ヒューマン・オルガノイド生命医科学」と「情報・数理科学」を世界で初めて本格的に融合するほか、こうした新たなアプローチでの研究に関する、倫理的・法的・社会的な側面の諸課題にも取り組んでいきます。